もも年長(1歳児クラス)にクマがやってきてくれました。(クマに扮したN先生)

くまさんがやってきてくれました もも年長(1歳児クラス)
いつも不思議に思うことがあります。
クマの帽子を付けているのはいつも見ている保育者なのに、どうして子どもたちは保育者をクマだと思ってしまうのでしょうか。不思議だと思いませんか?
幼児期の子どもたちは、あらゆるものが生きていると信じています。この現象をアニミズムというそうですが、言葉で簡単に終わらせることができません。
というのは、この感覚は子どものとき誰しも持っていた感覚なのです。私も3歳の時キングコングが街に表れる怖い思いをしたことがあります。(心理的にどう分析されてしまうかは置いといて・・・)サンタクロースもいまだ見たことはないですが、12月の時期になると心が温かくなります。想像してみてください。サンタクロースや節分の時に表れる鬼、本当にいたら・・・。子どもたちは、本気なのです。
このたびの実践は、追いかけ玉入れのアレンジバージョンです。
保育者は実践に思いを込めていくのです。ここに保育者の力量が問われるといえるでしょう。
先日、絵本の読み聞かせについてお話ししましたが、私は絵本は読み聞かせではなく読み合わせが大切だと考えております。
子どもたちの息づかいと歩調を合わせながら、お話を子どもとともに創造していくのです。
子どもを見る目がおのずと問われることとなるでしょう。
言葉の使い方はどうか、速いか、遅いか・・・、音楽と同じようにリズムが大切です。
心地よいリズムをかなでていきましょう。

Sちゃん、Cちゃんがんばって ゆり(4歳児クラス)

S先生も一緒に走って応援してますね いい汗かいてます! ゆり(4歳児クラス)

T先生 がんばって走った子どもたちをしっかり受け止めておりますよ ゆり(4歳児クラス)

紙芝居 落ち着いて聞いておりますね みかん(3歳児クラス)
そらまめも大きく育っておりますよ!

そらまめ
本日の保育実践を紹介します。
どうぞご覧ください。
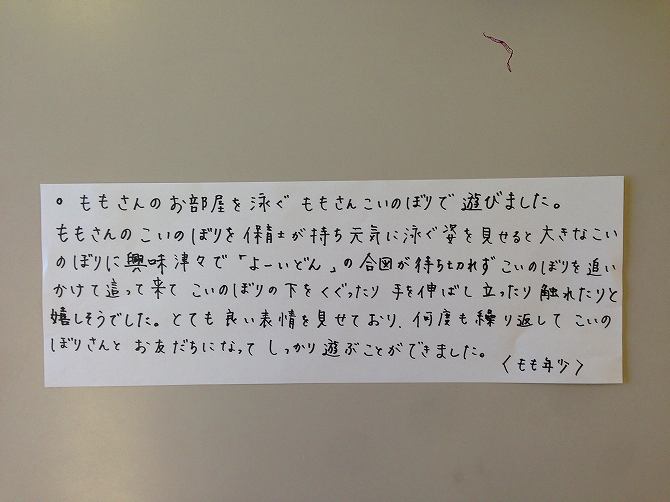
もも年少(0歳児クラス)
ももさんのお部屋を泳ぐももさんこいのぼりで遊びました。
ももさんのこいのぼりを保育士が持ち元気に泳ぐ姿を見せると・・・。(子どもたちは)大きなこいのぼりに興味津々な様子で、「よーいどん」の合図が待ちきれず、こいのぼりを追いかけるように這ってきて、こいのぼりの下をくぐったり手を伸ばして立ったり(触れたり)とうれしそうでした。こいのぼりさんとお友だちになってしっかり遊ぶことができました。
もも年少(0歳児クラス)
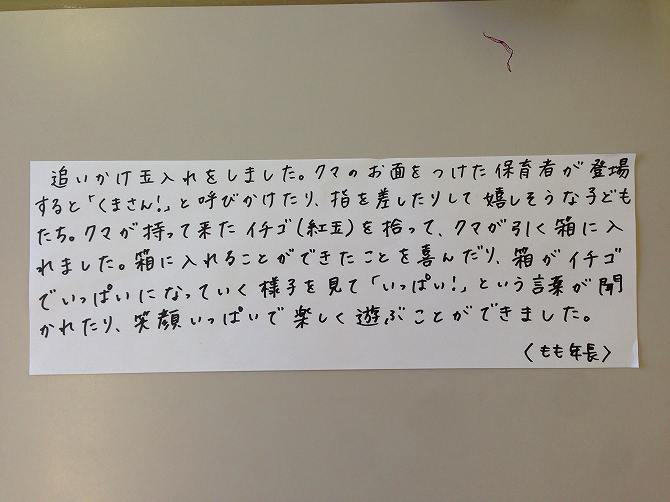
もも年長(1歳児クラス)
追いかけ玉入れをしました。
クマのお面を付けた保育者が登場すると「くまさん!」と呼び掛けたり、指をさしたりして嬉しそうな子どもたち。クマが持ってきたイチゴ(紅玉)を拾って、クマが引く箱に入れました。
箱に入れることができたことを喜んだり、箱がイチゴでいっぱいになっていく様子を見て「いっぱい!」という言葉が聞かれたり、笑顔いっぱいで楽しく遊ぶことができました。
もも年長(1歳児クラス)
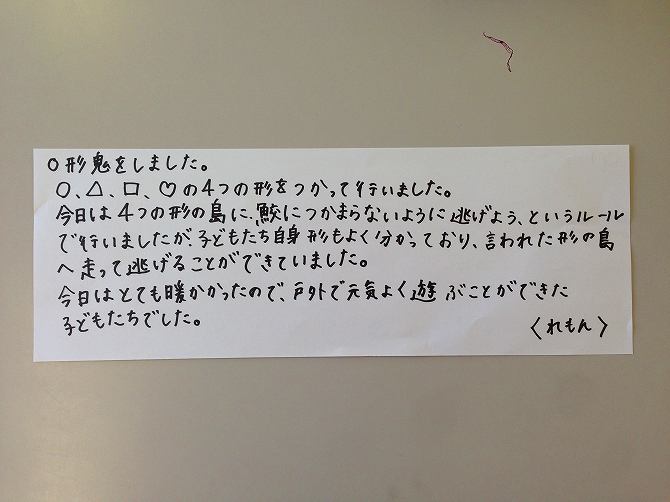
れもん(2歳児クラス)
形おにをしました。
まる、さんかく、しかく、はーとの4つの形を使って行いました。今日は4つの形の島に、鮫につかまらないように逃げようというルールで行いましたが、子どもたち自身形もよくわかっており、、言われた形の島へ走って逃げることができていました。
今日はとても暖かかったので、戸外で元気よく遊ぶことができました。
れもん(2歳児クラス)
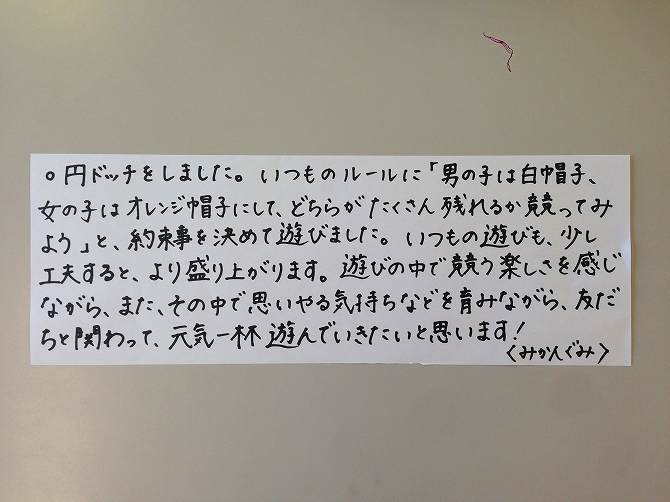
みかん(3歳児クラス)
円ドッジをしました。
いつものルールに「男の子は白帽子 、女の子はオレンジ帽子にして、どちらがたくさん残れるか競ってみよう」と、約束事を決めて遊びました。いつもの遊びも少し工夫すると、より盛り上がります。遊びの中で競う楽しさを感じながら、また、その中で思いやる気持ちを育みながら、友だちと関わって元気いっぱい遊んでいきたいと思います!
みかん(3歳児クラス)
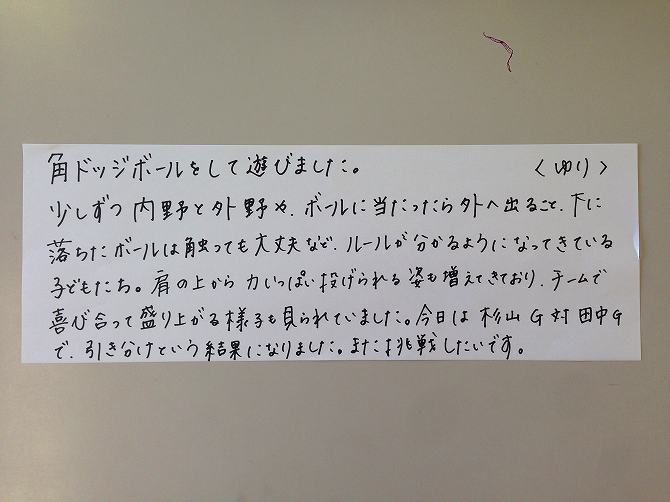
ゆり(4歳児クラス)
角ドッジボールをして遊びました。
少しずつ内野と外野やボールに当たったら外へ出ること、下に落ちたボールは触っても大丈夫など、ルールがわかるようになってきている子どもたち。肩の上から力いっぱい投げられる姿も増えてきており、チームで喜び合って盛り上がる様子も見られていました。
今日は杉山グループvs田中グループで引き分けという結果になりました。
また挑戦したいです。
ゆり(4歳児クラス)
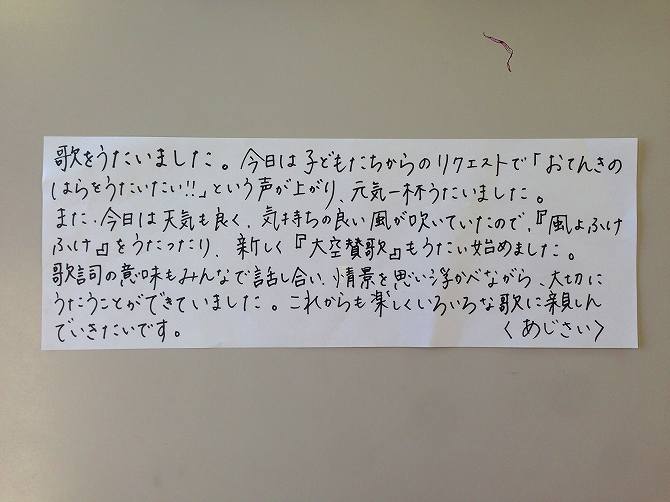
あじさい(5歳児クラス)
歌をうたいました。
今日は子どもたちからのリクエストで「おてんきのはらをうたいたい!!」という声が上がり、元気いっぱい歌いました。
また、今日は天気も良く、気持ちの良い風が吹いていたので「風よふけふけ」をうたったり、新しく「大空賛歌」もうたいはじめました。
歌詞の意味もみんなで話し合い、情景を思い浮かべながら大切にうたうことができていました。これからも楽しくいろいろな歌に親しんでいきたいです。
あじさい(5歳児クラス)